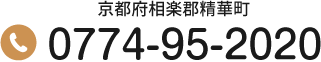ブログBlog
季節の変わり目に気をつけたい子どもの病気
季節の変わり目に気をつけたい子どもの病気
〜体調を崩さないためのコツ〜
「季節の変わり目は体調を崩しやすい」とよく言われます。診察中、私もよく言っていると思います。
実際、朝晩の冷え込みや湿度の変化により、子どもの体調を心配して来院されるご家庭が増える時期でもあります。
子どもは大人に比べて体温調整がまだ未熟なため、急な気温差や乾燥に敏感に反応します。ただし、寒暖差や乾燥そのものが病気を“直接”引き起こすわけではありません。これらは体へのストレスとなり、粘膜の防御機能を弱めたり、自律神経のバランスを崩すことで、結果的に感染症や持病の悪化につながりやすくなるのです。
季節の変わり目にかかりやすい主な病気
● 喘息(ぜんそく)
季節の変わり目は喘息の発作が起こりやすい時期です。特に朝晩と日中の気温差が大きい日は、ゼーゼーとした呼吸や夜間の咳が増えやすくなります。
また、梅雨や秋雨の時期は湿度が上がり、ダニやカビが繁殖しやすくなるため、アレルゲンによる発作も起きやすくなります。喘息をもつお子さんにとっては、一年の中でも注意が必要な季節です。
● アトピー性皮膚炎
秋から冬にかけて乾燥が進むと、皮膚のバリア機能が低下し、かゆみや湿疹が悪化しやすくなります。
かゆみが強いと夜眠れなかったり、集中力が落ちるなど、生活全体に影響を及ぼすこともあります。早めの保湿ケアが大切です。
● かぜ(かぜ症候群)
「寒暖差で風邪をひく」と思われがちですが、風邪の原因はウイルス感染です。
ただし、気温の急変や乾燥によって鼻や喉の粘膜が弱まると、ウイルスが体内に入りやすくなります。
季節の変わり目は、体調を崩したり感染症にかかる子が増えるのはこのためです。
ご家庭でできる予防の工夫
● 衣服でうまく温度調整を
気温差が5℃以上ある日は、体に負担がかかりやすくなります。
外出時は薄手の上着を持ち歩き、寝るときは腹巻きやスリーパーで寝冷えを防ぎましょう。
こどもは薄着で寝たがりますよね。衣服での調節が難しいときは室内温度設定に気を使いましょう。
● 室内環境を整える
乾燥する時期は加湿器を使って湿度40〜60%を目安に。
逆に梅雨や夏場は、窓を開けて風を通し、湿気をためない工夫を。カビやダニの繁殖を防ぐことができます。
● スキンケアの習慣化
入浴後10分以内の保湿が効果的です。乾燥の強い時期は1日2回の保湿を心がけましょう。
皮膚を守ることは、感染予防にもつながります。
ヘパリン類似物質泡スプレー(泡の保湿剤)をこまめに使うのがお勧めです。
● 睡眠と食事
睡眠と食事は免疫の土台です。夜更かしや偏った食事を避け、規則正しい生活リズムを。
目安として、未就学児は10〜12時間、小学生は9〜11時間の睡眠が理想です。
● 手洗い・うがいの徹底
帰宅後、食事前、トイレやオムツ替えのあとには、石けんで20秒以上しっかり手を洗いましょう。
感染症対策の基本ですが、最も効果的な習慣です。
まとめ
季節の変わり目は、寒暖差や乾燥といった環境の変化で、子どもの体に負担がかかりやすい時期です。
直接の原因にはならなくても、体の防御力を弱めてしまうことで、感染症や持病の悪化を招くことがあります。
「衣服で温度を調整する」「加湿と保湿で乾燥を防ぐ」「手洗いを徹底する」――
こうした日常の小さな工夫が、子どもの健康を守るいちばんの近道です。
そして、もし「いつもと違う」「気になる症状が続く」と感じたら、早めにご相談ください。
(参考:厚生労働省「子どもの健康と予防接種」/国立感染症研究所「感染症情報センター」/日本小児アレルギー学会ガイドライン)
最近の投稿
- こどもの下痢、どう対応する? 家庭でのケアと食事のポイント
- 子どもの体温が高いとき、すぐ受診すべき? 数字に振り回されない発熱の見方
- 第2回「ダウン症しばふひろば」を開催しました
- 赤ちゃんの哺乳量、心配しすぎなくて大丈夫!
- 季節の変わり目に気をつけたい子どもの病気